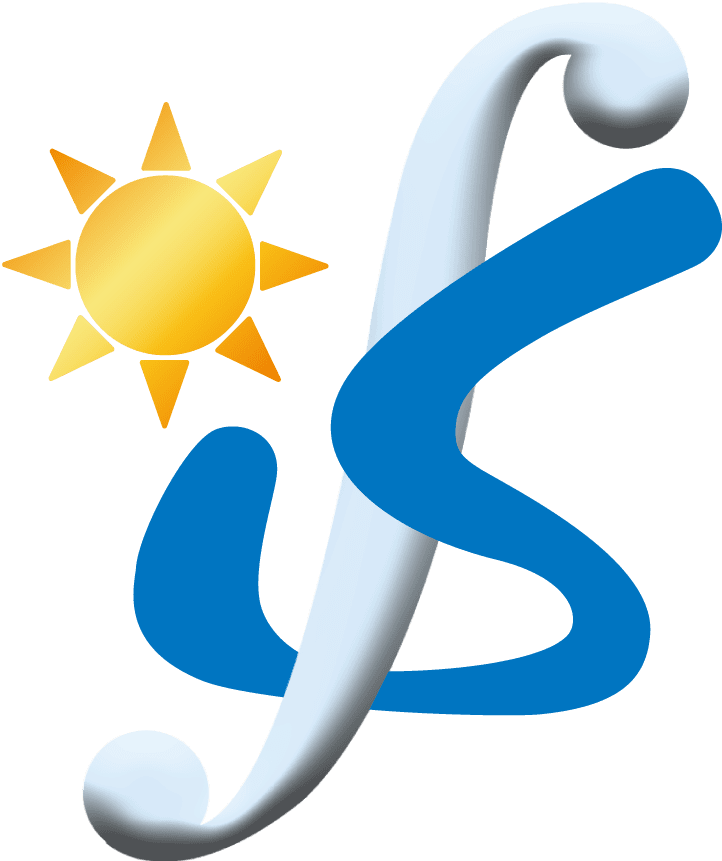私は母に連れられて港のバス停(終点。私達には出発点)にいた。
バスが来て、安全のため母が私を抱っこしようとすると私はそれを嫌がって拒否した。
私は四歳になったばかりだったが、弟が生まれ私は兄になっており、それが抱っこを拒んだ理由だ。
母とバスで出掛けるのは特別なことであり、私は上機嫌。弟をばあちゃんに任せ、母を独占出来るし。
しかし、バスに乗った目的はその日の朝、発熱した私をかかり付けの総合病院に診察に連れて行く事だった。
私ははしゃいでアニメの主題歌などを本気で歌っている。
で、病院の待合室で名前を呼ばれ、母と診察室に入る。
総合病院の理事長で院長の先生がニコニコと私を迎える。
「おおー、めんこい孫が来たなぁー」
後で、この人がばあちゃんの同級生だったと聞かされた。
私もニコニコと「やぁ」という感じで院長先生の膝元へ。
結果、風邪だろうということで、ペニシリン(当時の万能特効薬)の注射を打ちましょうと。
若い看護婦のお姉さんが、「はい」と応えて、煮沸消毒された器具の中から注射器を取り、薬剤のビンから白いペニシリンを充填した。
その辺りで私は、その後私に起こることを理解した。
で、「嫌だと」
始めは院長先生始め、看護婦さんも母も、「まあまあ、大丈夫だから」「すぐに終わるから」「やらなければダメなのよ」と、私を甘く見ていた。
五分後、診察室はしっちゃかめっちゃか。
トレーは床に落ち、カルテは宙を舞い、注射器は割れるの阿鼻叫喚。
その中で私は院長先生のスネを思い切り蹴ったのだけは憶えている。
結局私は診察室の中の異変に気付いて集まった大人たちに取り押さえられ、お尻に注射を打たれ、多分、その痛さよりも無理やり注射を打たれた事が悔しくて、本当に自分の耳にも残っているが、「おーいおいおい」と大声で泣いて、気付いたら家でばあちゃんの膝の中にいた。
「あれは弁償しないと」と母がばあちゃんに言う声で眼を覚ますと、ばあちゃんが優しい顔で、「あばれたな?」と私の顔を覗き込んできた。
私は、看護婦さんから注射器を奪って、壁に投げつけたことなどを思い出し、正直に「うん」と答えた。
「明日、ばあちゃんと病院へ行って、院長先生に謝ってくっぺ」と言われ、
私は「やだ」と答えたが、ばあちゃんに「だーめ」と言われるとそれ以上逆らえなかった。
それ以来、私は成長するとともにあの手この手で注射を避けて生きてきた。
小学校の集団予防接種では、学級委員の権限を発揮し、クラスの皆を整列引率し保健室へ移動、先生から名簿をあずかり私の名前のところに「済」と書き入れる。
クラスに戻る際には、それとなく腕をおさえて。
経口薬が有るにも関わらず、なんで注射なの。
なんで先の尖った金属を身体に刺さなければならないの。
こんな調子でも、幸い身体は丈夫に成長し、その後社会人になるまで、歯科以外の通院や診察の経験は無く、
24歳の時、朝、仕事を開始しようとすると、近くの席の課長秘書がやってきて、「咳をしているけど熱はどう?」と言った。
「風邪が流行っているから、病院にいっておいで」と。
当然のように「大丈夫」と答えたが、
「すぐだから、行ってきなさい」と姉のような命令。(姉はいないから分からないが)
まあ、仕事の進捗にも偶々余裕があったので、課長のところへ行き、社用車の許可証を借りて、守衛さんに訳を話して外出証を書いて、近くの会社の系列の病院へ向かった。
駐車場に社用車を停め、病院に入ったが、何年も受診の受付をしたことが無く、おまけに保険証の事なども失念していた。
とりあえず待合室に行くと、平日とはいえ、お年寄りがいっぱい。
途方に暮れて、帰ろうかなと思っていると、受付から出てきた白衣の方が、「外出証は?」と。
ああ、会社の上着を羽織っていたから分かってくれたのかと、ポケットからクシャクシャの外出証を出す。行先:病院。恥ずかしい。
しかし、それを受け取った白衣の方は、「じゃあ、あの診察室へ入って」と。
えー、あんなに待っている人がいるのにと驚きながら、診察室に入ると、先生と看護婦さんがいて、優しく「どうしましたか?」と。
熱を計られて、「風邪のひき始めかな」「早目に治まるように注射を打っておこうね」と。
「いや、先生、飲み薬で治るのであれば」と私。
「えっ」と先生。
「えっ」と私。
看護婦が「お注射の方が確実で早いですよ」と余計な事を。
久々に注射を怖がっているのを悟られるのを避けるように、「うーん、そうかぁ」と。
当たり前のように先生が、「じゃあ、そちらで腕を肩まで出して」と。
「あの、お尻では駄目ですか」と意を決した私。
看護婦がそっぽを向いて笑った気がした。
「いいですよ」と先生。
診察用ベッドに横になると、看護婦がカーテンを閉める。
「何で」とビビる私。
「お尻に注射をするんでしょ」と看護婦。
ああ、自分で尻を出すと言ったんだった。
最後、覚悟を決めて、「優しくお願いします」
とうとう看護婦は笑い出した。
「何歳ですか?」
「24です」真面目な私。
その遣り取りの間に、お尻にトンっと注射のショック。
ベッドに額を擦り付け、耐える。
アルコール綿で患部(私にとっては)を押さえ、多分背後で笑っている看護婦。
私は足を引きずるように薬局で薬を受け取り、受付に行くと、支払は要らないと言われ、普通なら「へえ」と思うところも何の感情も無く、
下半身を引きずるようにクルマに乗って、会社へ戻る。
また課長秘書が来て、「どうだった?」と。
私は青ざめた顔で、「重症」と。
「えーっ、じゃあもう今日は帰りなさい」
「うん、帰る」
あれから40年経った今も、アレルギーは改善されることはない。
コロナの予防接種も世の為人の為にやりはしたが、
テレビなどでその接種の場面(注射の場面)が流れると、即座にテレビを消す。
三つ子の魂百までとは言うが、あの時、大人たちに取り押さえられて打たれた注射は一生忘れない。
ゆう