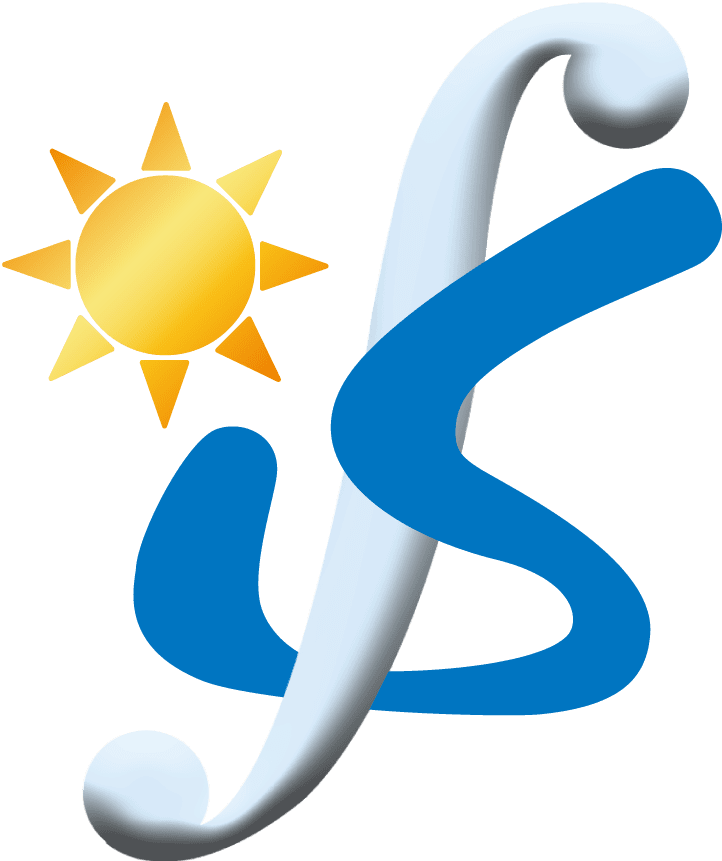もうかれこれ30年近く、海に触っていない。
何度か、時間を作って海へ行かなければと思いはしたが、思いだけが空しく立ち昇って、その距離はいっこうに縮まらない。
生まれてから十八で家を出るまで、常に海が生活の中にあった。
春夏秋冬、凪の日も台風の日も、太平洋の海の匂いが生活の中にあった。
私が生まれた町は小さな田舎町で、天然の波浮(はぶ)の港として古くから栄えた漁師町だった。漁業や漁業に関連する仕事に従事する人たちが多数を占める、島国日本の沿岸に在る、そんな町のひとつだ。
私が子供の頃は大陸棚から底引き網で獲れる高級魚が、交通網の発達に伴い東京築地に良い値段で大量に売れていた。
それゆえ、当時の漁師は良い暮らしをしていたと思う。最新の家電を揃え、最新の高級車に乗り、奥さんたちは月に一度東京へ芝居を観に行ったり、北海道から九州まで旅行をしたり。
ただし、一人船長の小さな船の生活はそれほど楽では無かった。時期的にシラス漁などで稼ぎが有ったとしても、通年では冬の荒天での休業が響き、年間の稼ぎとしてはそれほどでも無かったからだ。
その頃、親に食べさせてもらっている高校生の私は、父からこんな景気はあと数年で終わると聞かされても、何もピンと来ていなかった。
父曰く、海の水温が年々変わっており、それによって現在の漁獲量が減ってしまうだろうという事だった。もちろん底引き網漁という漁法も悪いと父は言っていた。
父は10余名の船員を束ねる船長(正しくは漁労長)をしており、出漁の前に天気予報の気圧配置を見て細かく操業海域の計画を組み立てる人だった。気象情報についてはとにかく詳しく、その上で、空を眺めて風と話す。という感じだった。
100トンの船を襲う荒波の上で、10人の命を預かっている仕事だということを、いつも責任として心の中に持っていたようだ。
仕事というものを背中で教えてくれた父をリスペクトしていたが、私は私で海の町に生まれて、私なりに海と向き合っていた。
小学生になると、校庭のジャングルジムよりも家の裏手の堤防を飛び越え、テトラポットの上を走り回っていた。テレビで忍者ハットリくんを観れば、テトラポットの上を両手両足でどれだけ早く走れるかとか。近所の人に見つかるといつも叱られていた。
しかし、港の先の堤防の端、そしてその先の海中から山のように積み上げられたテトラポットの端まで行くと、そこから先へは行けない。
ただ海がある。
そのことに、子供ながらに言いようのない寂しさを感じていた。
この先はもうアメリカなのかと考え、自分の立っている世界の狭さに絶望感のような寂しさを感じたのだ。私なりに私が変わっているのかと思い、そのことを母に話したが笑って相手にしてもらえなかった。
だから私はその場所を特別な「先っちょ」として、己の感性の変化を確認すべく何度も訪れた。
足下30センチ。消波ブロックとしてのテトラポットに波が打ち付ける。それは何も変わらない。突堤の先のテトラポットの先、ギリギリ波に濡れない所。背中にはテトラポットだけ、周りは海。
小学生の高学年になった私は、私なりに結論を出した。ここでいつも寂しい気持ちになるのは多分正常。まるでここはこの世の果て。この海の先は彼岸と同じ。
高校三年になった冬の夜、冷たい夜気の中で煙草を味わうために、私はそのテトラポットの先まで行った。
乾いたテトラポットにもたれて、煙草に火を点けた。
海面の高さは満潮・干潮があっても、今は足下30センチくらい。
煙草を吸いながら、海上40メートル先の灯台の光を見ていた。
星は少なく、灯台の光も寒そうだった。
その時、何かの動く気配を感じた。
良くない気配。じっと眼を凝らした。
灯台の、大きなコンクリートの土台の向こうに暗い大きな生き物のような、うねりが持ち上がっていた。
私は一瞬「ああ、死ぬ」と思ったが、取り敢えず悪足掻きでもその巨大な波の衝撃を避けようと、入り組んだテトラポットの波の反対側にぶら下がるように渾身の力で、しがみついた。大きなうねりは、海から5メートルくらいの高さの灯台の土台ごと飲み込んで、こちらに向かって来た。
ドーンという音とともに大きな波が積み上げられたテトラポットの上を越えていった。
背中にドドドという音を聞きながら、何とか海に落ちずに済んだ。
次の瞬間、私はテトラポットの上に飛び上がり、堤防の端を目指してリーガルの茶色のお気に入りのローファーで必死に走った。次の大波が来る前に堤防の端になんとか着地した。
私は煙草をまだ咥えていたことに気付き、プっと足元に吐き捨てると、またゴゴゴという恐ろしい気配。
防波堤としての堤防はあるが、波はそれを越えてくる。
堤防の端から安全なところまで50メートルはある。
迷う暇は無い。私は咄嗟にうつ伏せに地面に伏せた。
またドーンという音とともに大波が防波堤を越えて反対側の海にドドドと落ちていった。
最初の波では殆ど身体は濡れなかったが、二度目の波はもろに背中を叩いていった。
濡れネズミになりながら、ダッシュで堤防の上を移動した。
冬の夜、暗い海から何とか逃げた。
私は堤防の安全なところまで来ると、取り敢えず寒さも忘れ、近くのなにかの樽に腰を下ろし、ジーパンのポケットからショートホープとマッチを取り出した。
湿ってはいるが、濡れてはいない。一本咥えてマッチで火を点けた。
中まで濡れてしまったローファーを見ながら、今起こったことを反芻した。
海が俺を殺そうとした。と呆然とした。
海に暮らしていれば、冬の夜の海に落ちればどうなるか、誰でも知っている。
単に私がそれを甘く見ただけだ。
しかし、半年前にも小舟で湾内をお使いで移動しようとして、櫓が壊れて沖まで流され、あやうく死にかけたことがあって、何か海の意志を感じてしまう。
そして、この先に彼岸がある。と仮定した小学生のころの記憶と結びついてしまう。
それから私は海をひとつの生き物として考えるようになった。
その後もチャラチャラと海水浴などに行ったりもした。
しかし、海に対して油断しない。
私は海から得た糧によって育ててもらった。
その恩は恩として、あの震災の後の津波で私の町は壊滅的な被害を受けた。
ただし、海が生き物だとしても、私に怖さなどは無い。むしろ郷愁の方が強い。
東京に居ても、品川辺りに行って、海の匂いを感じると懐かしさでいっぱいになる。
海に食べさせてもらった。
海で遊ばせてもらった。
海で父母と暮らした。
夏の朝、早目に起きて、テトラポットを安楽椅子のようにして横になり、キラキラ光る朝の海を見ながら、海上を渡る優しい風を聞くのが好きだった。
今なら、父のように海風と話しが出来るだろうか。
ゆう