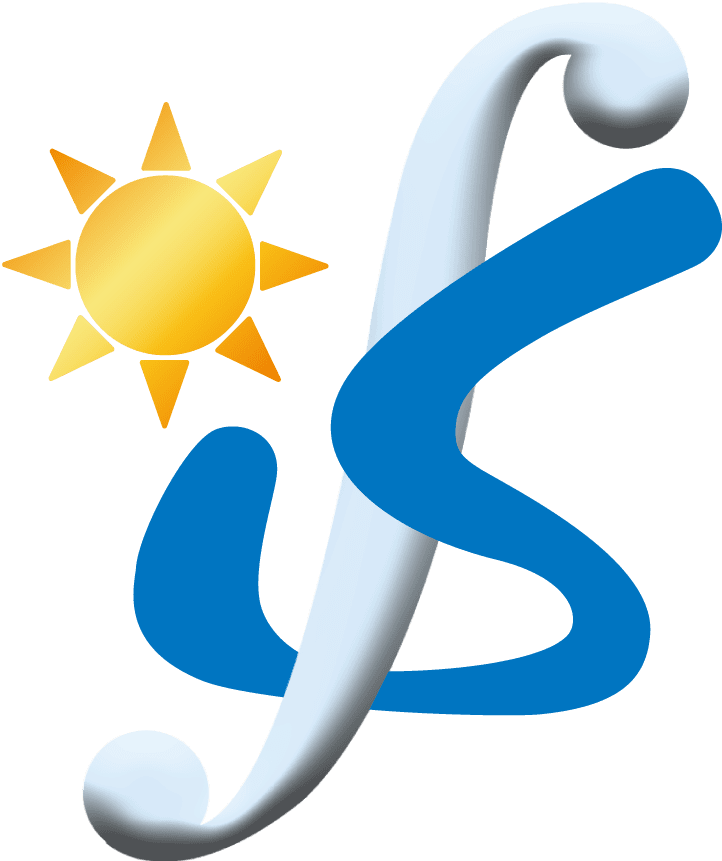私は生涯に一冊で充分なので小説を書きたいと思っている。
海辺の街で生まれ育ち、地元の企業に就職し、開発の世界で経験を積み、営業や経営も経験した。
しかし、その経験は小説を書きたいという動機とはあまり関係無い。
子供の頃から本が好きで、成長するにつれ一時期は活字中毒と思われる状態もあった。
9歳の時、近所の本屋で「ああ無情」(レ・ミゼラブル)を単にタイトルで選んで買い求め自宅で読んだ。
読み進めるうちに、私はその開いたページに涙をポタポタ落とし始め、気が付くと母が優しく小さな背中に手を当ててくれていた。
その時その時で小説は私に感動や驚きを与えてくれたが、はっきりと自分の生き方に影響を受けるだろうなと感じながら読んだのは、司馬遼太郎の「燃えよ剣」からだったと思う。
当時私は中学生で剣道部に所属しており、サッカー部に入りたくないという邪な理由で始めた剣道だったからか、5名の同級生の中で私は一番弱く、「燃えよ剣」は図書館で何となく不貞腐れた気持ちで手に取った新しい文庫本だった。
それは上下巻だったと思うが、読み始めてその面白さにすぐに貸出しを申し出て、4日ほどで読了した。
ついで予てより手に取ってみたかった、吉川英治の「宮本武蔵」を通学途上の田舎では大き目の書店に立ち寄って購入した。
吉川英治は戦後の流行作家とでも言うべき人だが、「宮本武蔵」の文庫の帯に『敗戦後の日本で仕事が上手くいかず自殺を覚悟した人が、傍らの新聞に毎日掲載されている小説欄の「宮本武蔵」の、武蔵が決闘に出掛ける場面を読んで改めて生きようと思い直した』というエピソードの投書があったと書かれていた。
その時の私は部活の剣道に対して徐々に、強くなりたいと思い始めており、満を持して「宮本武蔵」を読んだ。
文章を読んで、まず宮本武蔵ではなく吉川英治が、(当時は僭越を越えているが) 人生の達人なのだろうなと思った。
文章の編集や推敲をしないことは無いだろうが、なんと流麗で静謐な完成された文章かと恐れ入った。感化されるとはこういうことかというくらい吉川英治に興味を持った。
「国取り物語」や「太閤記」、果ては「三国志」など、(僭越ながら)当時の日本人を喜ばせる作品の数々。
私は吉川英治のデビュー作を調べて、それから全集を読み漁った。
現在では大作家として、小説の大きな賞の冠にもなっているが、私はその人となりにも興味を持ち、関連するインタビュー記事や短文・エッセイの類まで読ませてもらった。
特に、奈良の吉野で娘さんと2人、美しく広がる山々の桜を背景に、そのお嬢さんの結婚について取材を受ける吉川英治の写真を見て、私はいつか自分の眼で奈良の吉野の千本桜を見て、「美しいな」とつぶやいてみたいと心に決めている。
その時、吉川英治は「お嬢さんのご結婚について何か云う事はありますか?」との記者の質問に、頭を下げて「娘を宜しくおねがいします。」とだけ涙を湛えて応えたと書いてあった。
老境にさしかかる当時ナンバーワンの大作家でありながら、さすがの人間性だと妙に感銘を受けたのを記憶している。
それ以外に全作品を読ませてもらった作家は何名もいらっしゃるが、やはり山本周五郎と藤沢周平は私の中で別格だ。
お二人とも其々にストーリーテラーとして紛れもない「天才」だと異論は無いだろう。
人情の機微と人生の論理。行間にまで溢れる情念と理(ことわり)はいつ読み返しても圧巻だ。
本当に少しは他の小説家のことも考えてくれと言いたくなるほど。
しかし、それでも私が一番心を惹かれ、己の生き方として進んでその影響を「受けたい」と思っているのは、志水辰夫さんの小説で、私のナンバーワンは「あした蜉蝣の旅」という作品だ。
その小説は志水辰夫さんの作品の中では、読者ランキングは高くないが、そんなことは私にはどうでもいい。
北陸の暗い空から始まって、北海道西部の島を襲った津波を題材にし、最後は北陸の小さな港町に戻る物語だが、最後の1ページで文字を追う眼が止まってしまい、「この結末に向かって長い物語が書かれていたのか」と、「凄い」というため息しか無かった。
何かのアニメのセリフにもあったが、「恰好良いとはこういうことだ」と。
多くのミステリーやハードボイルド作家が苦心して求めているものを、志水辰夫さんは始めから理解しているように感じる。
現在 86歳で、19年振りのハードボイルド作品をこの10月3日に上梓された。
タイトルは「負けくらべ」。
多分、志水辰夫さん最後の作品になるだろうとのことだ。
大型の書店に何回か足を運んで、やっと手に入れた。
新刊本の帯には錚々たる作家陣が賞賛の寄稿をしている。
見たくないけど、本文紹介として一部抜粋が書かれていた。
「ぼくはだいたい人間関係をいちばん不得手にしているんです。これまで育ってきた環境が、情感とは無縁の、論理の世界でしたからね。人情というものがいまでもわからないのです。一方あなたはずっと人間関係の中で生きてこられた、人生の達人です。数値には表せませんが、両者の隔たりはとてつもなく大きいんです。譬えていうならケア(CARE)とキュア(CURE)のちがい。ケアは気配り、介護、寄り添う、キュアは治療、救済、矯正、両者には歴然とした違いがあります。キュアで足りないものはケアで補うしかないんです」
私は「イヤー(ン)、志水辰夫さんだー」と書店の中で叫んでいた。
カテゴリで言えば、ミステリーとハードボイルドの中間でシミタツハードボイルドなどとファンの間では言われているらしい。
そんなことよりも蜉蝣(かげろう)のような、風に持っていかれそうな、取るに足らない社会、いや世界の片隅のたったひとりの人間というものをどうしたらこんなに恰好良く意味付け出来るのか。
勿論、こちらが勝手に恰好良いと思ってしまうのだが。
私は自身の興奮を抑える為、他の作家の新書刊小説も何冊か選んで、「負けくらべ」以外はレジに忘れそうな勢いで、幸せ気分で家に帰り、「負けくらべ」だけ眼に入る所に立てかけて、チラチラ見ては「ふぅーっ」とため息をついている。
多分、読み始めたら途中では終われない。
なので、そのタイミングをはかっている。
子供の頃、様々に読書感想文を書いて、その都度小学校の先生に絶賛された。
喜び勇んでそれを母に見せると、母から「大きくなったら、ゆうちゃんの物語を書いてみなさい」と言われた。
それはずっと胸に残っている。
そして、母が亡くなる前に、入院していた母のベッドにずっと付き添っている時、急に母から「小説はまだ書かないの?」と言われた。私はすでに四十のおっさんになっていた。私は面食らって「何それ」と言うと、「書きなさい」と念押しされた。
私は「……」言葉に出来なかったが、母の眼を見てはっきりうなずいた。
母の生前には叶わなかったが、必ず母に報告出来る小説を書きたいという野望がある。
そう、志水辰夫さんの作品のような。
もちろんリスペクトだけで到底届かないのは分かってはいるが、蜻蛉のように風に飛ばされる存在のような私自身を小説にして、母への手土産にするつもりだ。
母に褒めてもらえるような小説が書けるだろうか。
ゆう